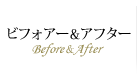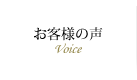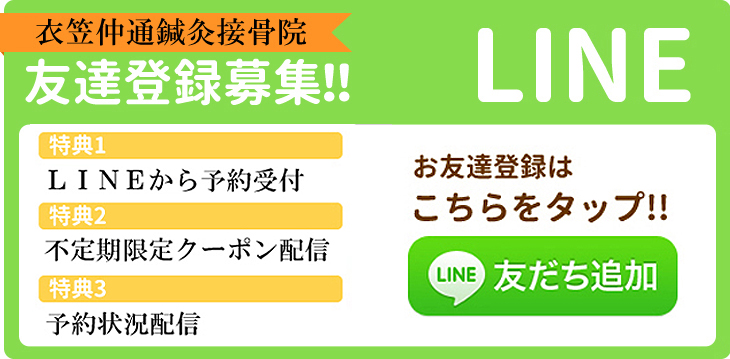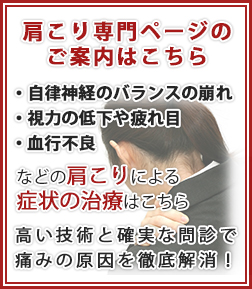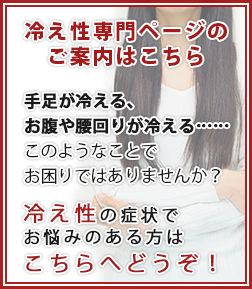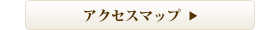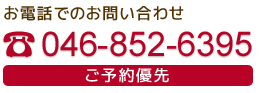「冷え性」を解消して美しくなるための5つの生活習慣

上田式美容鍼灸Ⓡ、衣笠仲通鍼灸接骨院院長の加藤宏です。
寒い時期になると気になるのが「冷え性」。
夏でも冷房などで冷える方は多いですが、やはり気温が下がるこの時期は特に気になるのではないでしょうか?
冷え性は女性に多いお悩みです。
「冷えは万病の元」と言われるように、体に悪影響があるだけでなく、気になる美容のお悩みにもつながります。
「冷え性」って何?

「冷え性」とは、体温が低い「低体温」とは異なり、体内での温度差が大きい状態を言います。
外側は温かいのに中心部のお腹が冷たい等の状態の事で、良くあるのは手足の先が冷えてしまう「末端冷え性」です。
身体はどのように温まるの?
体内では、熱は代謝によって作られます。
代謝には三種類あります。
-
生活活動代謝
運動をしたり、生活の中で体を動かしたりといった時に熱が作られます。
このエネルギー代謝を「生活活動代謝」と言います。
作られる熱全体の20~30%を占めます。
-
食事誘発性熱産生
食事をすると、胃腸では消化・吸収をする時にエネルギー代謝が起こります。
これを「食事誘発性熱産生」と言います。
摂取した物によって発生する熱は変化します。
炭水化物、タンパク質、脂質の中ではタンパク質の消化吸収の時に最もエネルギーを必要とし、熱を発生します。
全体の10%程度を占めます。
-
基礎代謝
人間は何もしなくても生きていくためには体温を維持したりするために内臓を働かせています。
このように、生きているだけで起こるエネルギー代謝を「基礎代謝」と言います。
全体の70%程度を占めます。
基礎代謝が起こるのは肝臓が約37%、腎臓が約10%、筋肉が約25%を占めます。
何故「冷え性」になるの?

自律神経のバランスの乱れ
不規則な生活、ストレス過剰などの原因により自律神経のバランスが崩れます。
自律神経は体温を調節する働きが有り、バランスが崩れると冷え性の原因になります。
血行不良
循環器系の疾患が有る方や低血圧、筋力不足、矯正下着による過度な圧迫などが有ると血液の流れが悪くなります。
また、自律神経のバランスが崩れ交感神経優位の状態では血管の収縮が強くなり血行が悪くなります。
血液の循環には「熱を伝える」という役割が有るので、血行不良により熱が伝わりにくくなり冷え性の原因になります。
偏った食事
無理なダイエットなど、偏った食生活により栄養のバランスが悪い事も原因の一つです。
タンパク質の不足は筋肉の低下につながり、またビタミンの不足なども冷え性の原因になります。
「冷え性」が女性に多いのは何故?
「冷え性」は女性に多く見られる症状です。
先述のように、基礎代謝の25%が筋肉で起こります。
女性は男性に比べると筋肉が少ないので、作られる熱も少なくなります。
熱を伝える為に重要な血液循環には筋ポンプ作用が関わりますが、筋肉が少ないと流れが悪くなり、やはり冷えやすくなってしまいます。
そして、女性は男性に比べて体に脂肪がつきやすくなっています。
脂肪は熱を伝えず、その為熱が伝わりにくくなり、さらに保冷剤のような役割を果たして冷えてしまった体を冷たいまま保とうとしてしまいます。
作られる熱が少なく、冷えた状態を保持してしまう事により冷えやすくなってしまうのです。
どうして身体が冷えると良くないの?

代謝が落ちる
内臓は温かい方がよく働き、冷える事で働きが悪くなります。
例えば肝臓や腎臓の冷えはエネルギー代謝が落ちてしまいます。
代謝が落ちると必要となるエネルギーが足りなくなり体調も悪くなります。
さらにエネルギー消費が落ちる事で摂取したカロリーが余ってしまうと脂肪に変って体に蓄積されてしまう為、肥満の原因にもなります。
疲れやすくなる
エネルギー代謝が落ちる事により疲労の回復力が落ちて疲れやすくなります。
また、人間の睡眠の質には体温が関わっています。
眠っている時に体温が下がる事によって深い眠りに入る事が出来るからです。
元々体が冷えてしまっている状態ではさらに体温を下げる事が難しく、睡眠の質が悪くなってしまいます。
睡眠には量だけでなく質も大切であり、質が悪い睡眠ではしっかり疲れをとる事が出来ません。
免疫力が落ちる
外部からの細菌、ウイルスなどの異物から体を守る免疫系の働きは体温が高い状態で力を発揮します。
風邪をひいた時に熱が出るのはウイルスと闘いやすくするために体温を上げて免疫を活発にする体の反応です。
身体が冷えていると免疫力が低下し、外部からの刺激に弱くなり感染症などの病気にかかりやすくなります。
肩こり
冷えて血行が悪くなると筋肉の緊張が強くなります。
筋緊張が強いと体は血流を回復させようとして「プロスタグランジン」という物質を発生させます。
プロスタグランジンは血管を拡張して血流を良くする働きだけでなく、痛みを発生するという働きも有ります。
こうして痛みが出るとさらに肩こりはつらくなってしまいます。
月経痛が重くなる
生理のお悩みで多いのが月経痛(生理痛)です。
月経時には子宮は経血を体外へ出そうと収縮します。
この時、子宮内膜からは血管を拡張するプロスタグランジンが分泌されます。
プロスタグランジンの働きによって腰痛や腹痛、血液によって運ばれると頭痛を引き起こす事も有ります。
冷え性の場合、血液循環が悪い事から骨盤内でうっ血が起こったり子宮が硬くなる事が有り、月経痛を重くしてしまう事があります。
美容のお悩み
気になる美容に関してはどうでしょうか?
何と言っても、
「顔は心と体を映し出す鏡」
冷えによる体への悪影響はお顔にも現れてしまいます。
お顔は肌が露出している時間がほとんどですので冷えやすい箇所でもあります。
血流が悪くなると血色が悪くなり、お肌はくすんで見えるようになります。
冷えによる血行不良で起こる「くすみ」は血流が良くなればすぐ改善します。
血液は細胞を元気にする酸素や栄養素を運ぶ役割が有るので、血行不良により細胞は栄養が不足します。
こうなると代謝が低下して細胞の機能が衰え「むくみ」や「肌荒れ」、「乾燥肌」といった肌トラブルの原因になります。
肩こりがひどくなると首の所で血流が悪くなりお顔への血行不良が起こるだけでなく、お顔につながる筋肉が緊張してしまいフェイスラインを下げてしまう原因にもなってしまいます。
冷えや肩こりの悪化で循環が悪くなるとお顔のむくみが起こり、頬が重たく下がるとほうれい線が目立ったりフェイスラインが下がったりする原因にもなります。
冷え性を予防・解消する5つの生活習慣
1.食生活のバランス
既にお話したように、食事をする事でエネルギー代謝が起こり、体では熱が発生します。
食事において重要な三大栄養素の「炭水化物」、「たんぱく質」、「脂質」の内、消化吸収によって最も熱を発生するのは「たんぱく質」です。
タンパク質は血漿タンパクや筋肉に関わる物でもあるので血液循環や基礎代謝にも関係し、不足しないよう十分摂取する事が大切です。
こちらもご参照ください↓
タンパク質が美肌を作る~プロテインの美容効果とは?
2.アルコールを摂り過ぎない
アルコールは体内で分解されることによって「アセトアルデヒド」という物質に変化します。
アセトアルデヒドは血管を拡張する働きがあります。
その為、熱が逃げやすくなり、結果的に身体は冷えやすくなってしまうのです。
適度なお酒は血行を良くして体を温めますが、過度な飲酒は逆に身体を冷やしてしまうので要注意です!
3.適度な運動
男性に比べて女性が冷えやすい理由は「筋肉が少ない」「脂肪がつきやすい」でした。
冷え性の改善には運動も有効です。
筋肉が増えれば代謝が上がり、その結果、脂肪も落ちやすくなります。
特に、お尻や脚、背中など大きな筋肉を狙えば効率よく代謝を上げる事が出来ます。
また、流れが滞りやすいふくらはぎを鍛えれば筋ポンプ作用により全身の血液循環をアップできます。
ふくらはぎが「第二の心臓」と呼ばれるのはその為です。
4.入浴は湯船につかる
ついシャワーで済ませがち、という方も多いかもしれませんが、シャワーだけでは体はきれいになってもなかなか温まらないものです。
特に冷え性の方は湯船にしっかりつかる習慣をつけて頂きたいです。
だからと言って無理に熱いお湯につかるのは交感神経優位になってしまって逆効果です。
40℃程度のお湯にゆっくりつかる事で副交感神経が高まり、血液循環も良くなるのでさらに体は温まります。
寝る前の入浴では、熱いお湯では交感神経優位になって睡眠の質が下がります
身体を温めてリラックスしてグッスリ眠れるようにぬるめのお湯にゆっくりつかりましょう。
5.服装にも注意!
スカートやストッキング等、女性の服装は身体を冷やしがちです。
気温が下がる冬でも足を出している女の子も多いですが、将来冷え性に悩まされないかが心配…
露出が増えれば、衣類が薄くなれば、当然体を冷やしてしまいます。
直接肌を出すのを控えるのはもちろんですが、例えば下着でも面積の多い物の方が体を冷やしにくいです。
しかし、ピッタリしてきつい衣類では体を圧迫して循環を悪くしてしまい、逆に冷えやすくなります。
また、汗が出る程の厚着は熱を逃がしてしまい、こちらも体を冷やしてしまいます。
まとめ
身体の状態はお顔に現れます。
美容鍼灸では自律神経のバランスを整え、血流を改善して体を温めます。
そして、お顔の鍼は局所の血液循環を良くして肌質やくすみを改善します。
しかし、いくら鍼をしてもその体を作るのはみなさんの生活習慣です。
美しく健康になる為には生活習慣が大切です。
身体を冷やさない為に5つの生活習慣に気を付けてみましょう。
まずはお気軽に問い合わせください
 まず、今すぐ下に表示されている番号へ、お電話ください。
そうすると衣笠仲通鍼灸接骨院の整骨院のスタッフが電話にでますので
『ホームページを見ました。予約をしたいのですが』とおっしゃってください。
まず、今すぐ下に表示されている番号へ、お電話ください。
そうすると衣笠仲通鍼灸接骨院の整骨院のスタッフが電話にでますので
『ホームページを見ました。予約をしたいのですが』とおっしゃってください。
あとはスタッフがあなたの症状などをお尋ねしますので、 簡単で構いませんので希望の施術日とご希望をお伝えください。 これでご予約は終了です、電話を受話器に置き電話をお切りください。 皆様のご来院をスタッフ一同心よりお待ちしております。